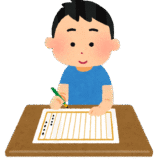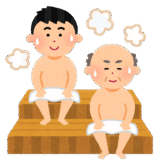Kindle Unlimitedではランダムに本を紹介してくれるのだけど、ふと目に止まったのがこれ。

「おかしな転生」の方ではなくて「不確実性超入門」の方な。
「おかしな転生」の方は以前24巻までUnlimitedで読んでたのが、いつの間にか29巻が発売ということで28巻までがUnlimitedになったので一気に読んだ。
何か深刻なトラブルがあっても、次の章ではとんでも能力を使って解決してしまうという、ある意味安心して読める本。
嫌いじゃない、というかむしろ好き。
ということで「不確実性超入門」
気に入ってるYoutuber「S&P500最強伝説」でもたまに紹介している本だったので読んでみる。
ま、簡単にいうと「予測できない未来=不確実性」と日常、ビジネス、投資の意思決定局面でどう向き合うかという思考法や実践例。
不確実性を量子力学的な面からも言及されていて、量子力学的には現在の状態は常に確定されておらず、(一つの量子が)動いていることと止まっていることは並列する普通の状態で、確認されて初めて状態が確定されるのだから何が起こるかわからないよ、と。
じゃあ「シュレンディンガーの猫」はどうなるのと思ってAIに聞いてみたらそれはマクロの話でミクロの話とは違うんだってばさ、というような説明をされてしまいました。
実例の一つとしてサブプライムローンが引きおこしたリーマンショックの話もでてくるのだけどもこれも発端から考えると「バタフライ効果」であったと。
バタフライ効果は「ブラジルの蝶の羽ばたきがテキサスのトルネードを引き起こす」というものだけれどもこれよりは、個人的には「風が吹けば桶屋が儲かる」のほうが好きです。スターアポロンVSタイガーマスクの試合でウルトラタイガードロップを封じられて困っているタイガーマスクにジャイアント馬場がかけたセリフとしても有名ですね。ただ猫が不幸になる話なので申し訳ないと言えば申し訳ない。
話、戻りなさい。
不確実性の中で気をつけなればならないバイアスは以下の4つ。
1)自己奉仕バイアス
過去成功したのは自分が優秀だから。
2)サンクコスト効果と自己正当化バイアス
山崎元さんの本でもお馴染みサンクコスト。
これだけ費用を突っ込んだんだから、そろそろ報われても良いでしょう
3)感情バイアス
当事者になると合理性・客観性を失ってしまう。
自己正当性バイアスにつながるかもね。
ぼくの持ち株TESLAとINTELは可愛い。
4)同調バイアス
多数派や権威への追随。
S&P500全ツッパ、本当にそれでいいの?って話。
ということで、この本の結論は「すべてを予測するのは不可能」だから確率や長期視点で行動し冷静に対処しましょうね、と身もふたもないような話。
なんだけど、宝くじを買う時、当選確率が変わらないとすれば、購入者や販売本数が増えれば当選本数は増えるけれど、それは自分の確率が高くなるわけではなくて他人が当たる確率が高くなるって話はなんとなく気に入った🤣
 長い夏休み
長い夏休み